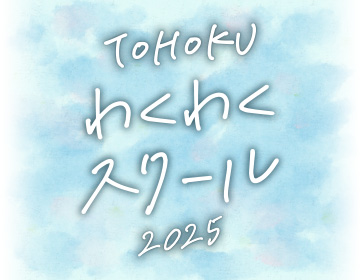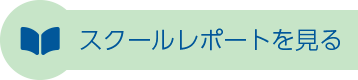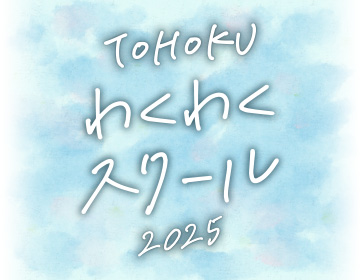
新潟県:新潟市立有明台小学校(小学6年生 36名)
テーマ:「教訓は、いのちを救う」~過去の災害から防災を学ぼう~
講 師:一般財団法人3.11伝承ロード推進機構
自然災害には地震や台風、大雨、火山の噴火など様々な種類があり、それらの災害によって、自分たちの住んでいる場所では、津波や河川の氾濫、堤防の決壊、土砂災害、火災など、どのような災害が起こりうるか、また、その災害に対して自分たちに何ができるかを考えた。東日本大震災と令和6年能登半島地震を例に、発災後に起こった津波の状況や、ライフラインの寸断(停電・断水)、液状化などの様子を、講師の実体験や写真を通して理解した。今後もどのような災害が起こりうるか分からない中で、「自助」(自分や家族の命を守ること)、「共助」(近所の人や周囲の人たちと助け合うこと)、「公助」(国や自治体、消防や警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助)に必要な日頃の備えや災害発生時の行動について学習した。体験学習では、避難所での疑似体験として、3m×6mの空間にクラスごとに入り、避難所の狭さを体験し、避難所で起こり得る困りごとについて、どのような困りごとが起きるか、どのような解決策があるか、自分たちにできることは何かについて考えた。最後に、今後の防災に役立てるために、伝承することの大切さについて学習した。
感想
- 一番心に残っていることは、誤って伝承された事例です。誤った伝承を信じてしまったために命をおとしてしまうのは切ないなと思いました。この悲しい歴史をムダにせず、前が大丈夫でも次の災害の方が大きいと想定して備えたうえで、正しく伝承することが大切だと思います。
- 津波のことを正直あまり調べたことがなかったので、大きな地しんが来たら津波がくるということしか知りませんでした。ですが、津波の速さは沖だとジェット機なみに速くて、かべのように押し寄せてくると言っていたので、そんなにおそろしいのだなと思いました。
- 自分の命は自分で守る、必ず生きて帰るという覚悟が大切ということが分かりました。災害時に生きのこることの難しさを知りました。
- とくにおどろいたのは、ひなん所のスペースの広さです、最初は「意外と広いんだな」と思っていましたが、人が多いひなん所のスペースは、子どもが体育すわりをして、やっと入れる位の広さだったり、知らない人といっしょにねることがあったり、そんなことがあるんだなと勉強になりました。